こちらの続きその2です。
タイトルにあえて「女性」と入れました。
まだまだ日本の女性は自分が主体的に稼ぐという意識が低いと思います
(学生時代の私はまさにそうだった)
べつにバリキャリを目指さなくてもよいと思います。
自分のペースで細く長く。たとえ収入がわずかでも、収入がある=プラスというのは大事です。
我が家の場合は、夫の方が私よりもだいたい1.5倍くらいは稼ぎますし、夫の収入だけでやっていけないことはありません。
でも、これからもその収入が続くかわかりません。人生何が起こるかわからないのだからこそ、リスクヘッジのため、収入源=働き手は多い方が良いでしょう。
一方で、共働き家庭で気になることと言えば、
① 働き損にならないか(いわゆる103万円の壁。今年から150万円に引き上げ)
② 保育園料の負担
ですよね。
①働き損にならない働き方ですが、パートで働いている方などが直面する問題でしょうか。
妻の収入が、ある一定額(今年から150万円)を超えると、夫が得られる所得控除=配偶者控除が得られなくなる。
つまり、せっかく稼いでも、収入額によっては、その家庭の手取り収入が夫だけが働いていたときよりも減ることもあると言うことです。
※ 配偶者控除
妻の収入額等の要件を満たすと、夫の所得から38万円が控除されて課税所得
が減り、結果として税金が安くなる
(この説明は、専門家ではない私が、ニュースを聞きかじって得た知識で
書いた、大雑把なものです。)
個人的には、所得控除のメリットのために収入を調整して働くと言うのは、収入を増やす機会を自ら逃していると言う点、労働力が足りないと言われている日本の状況から見ても、もったいないと思いますし、本末転倒な制度だなーと思います。
でも、子どもが小さいうちは、つきっきりで面倒をみてあげたいと考える女性もいらっしゃるでしょうし、事情があって(親の介護とか、ご自身の体調とか)働けない方のことを考えると、配偶者控除を必要とする人も多いんでしょうね。
全員をケアできる社会の仕組作りってなかなか難しい。
話がそれました、、
あと共働き家庭を悩ませるのは、②保育園料の負担ですね。
保育園料で、妻の稼ぎがほぼ消えるなんて話も聞いたことがあります。
実は、私も育休中、我が家の保育料がいくらになるのか気になって、役所の資料とにらめっこしていました笑
今、そこそこの金額を毎月お支払いしていますが、それに文句は言うつもりはありません。
なぜなら、保育士さんたちが本当に立派だから!!
オムツ替えや食事の世話に、一緒に遊んで、抱っこをせがまれたら抱っこして…
土日に、夫と私の2人体制で娘一人の相手をするのも大変なのに、保育士さんは何人も面倒を見てくださる…本当に頭が下がります。
相当な体力と忍耐力が必要な仕事なので、保育料は適正料金にして、保育士さんの待遇問題を改善してほしいと思っています。
でも、保育料で自分の稼ぎが消えるというのはなかなか複雑な気持ちになりそうですね。
朝、子どもを送って、我が子の泣き声を背中越しに聞きながら必死で働いて、それでは何のために職場復帰したんだろうって。
我が家は、幸い4月から認可保育園に入れたので、保育料で私の収入が消えると言うことはないです。
(実は今の認可保育園に入れる前に、認可外保育園に入れていたのですが…この話はまた別の機会に。保活に関してはプロです笑。語れることがたくさんあります!)
仮に私の収入がほとんど保育料に費やされる状況だったとしても、たぶん仕事に復帰していたと思います。
残念ながら現在の日本の雇用制度では、ブランクがあるとなかなか復帰できないので。
保育園料がかかるなんて、社会人時代の中でほんの数年のことですしね。
お金があれば、より選択肢が増えますから。
食べるもの着るもの、住む家・住むエリア、子どもの教育、趣味娯楽、老後の生活…
本当は誰しも平等に、ある程度の水準の生活は確保されるべきなのに、お金でそれを確保しようと必死にならなければ行けないなんて世知辛い…
そう思いますが、これが現実なのであきらめて受け入れて、うじうじ悩むよりもより良い生き方を模索する方に意識を向けたいものです。
だから、目先の損得は置いといて、できるだけキャリアを継続して、収入を確保する、できれば昇給・昇進を目指す。
それが大切なんじゃないかと思うのです。
かやこ
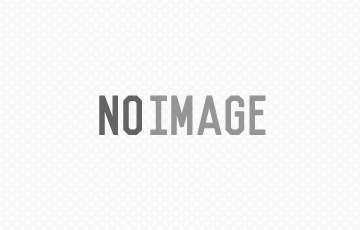


コメントを残す